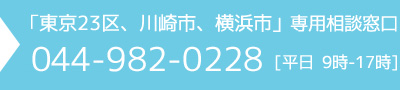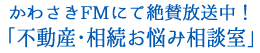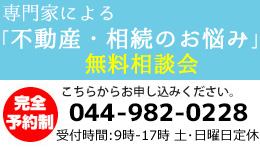不動産・相続のお悩み相談
間に合いそうにもありません
昨年秋に母が亡くなり相続で弟と話をしているのですがうまくまとまりそうにもありません。
私としては穏便に済ませ10か月以内にと目論んでいたのですが、今と..もっと見る
遺産がどれだけあるか調べる方法は?
父は脳梗塞で入院後体調が優れません。
最近では精神的に不安定な状態が続き、医者にはもってここ1年だろうと言われています。
因みに父には兄弟はいない..もっと見る
離婚した元夫との共有名義のマンションの税金について
8年前に結婚をし、6年前に品川の某所に新築マンションを購入しました。
2年前に離婚した元夫と、共有名義(1/2)マンションを所有しています。
そのマンショ..もっと見る
借地契約を解約したときに、地主さんからはいくらか支払いをしてもらえるものでしょうか?
旧法借地契約で20年契約を結んでいるのですが13年目の今年契約を解約しようと思っています。
こういう場合幾らか戻ってくるのでしょうか?
相続について教えて下さい。
我が家の相続について相談させて下さい。
実は両親は私が15歳の時に離婚しました。(親権は母親)
現在私は31歳、3人兄弟の次男で、兄と妹がいます。
父..もっと見る
B型肝炎キャリアであることが判明しました。
学生時代に献血して自分自身B型肝炎キャリアであることが判明しました。
今ネットで見て情報収集し調べているのですが、訴訟の対象になるんじゃないかと思い..もっと見る
借地権の地代について質問です。
母が借地に店兼自宅を建て直すことになりました。
30年前のことです。
その時に、色々ともめて、お互い弁護士をたてて調停となり、和解しました。(こちら..もっと見る
遺言書がある場合、寄与分は絶対認められないのでしょうか?
母が昨年亡くなりました。
介護は私が中心で、自営の弟は会社がうまくいっていなかった事もあり、その上離婚しシングルファーザーだった事もあり姉である私に..もっと見る
夫に養育費の前払いをさせることは可能ですか?
今夫との離婚を考えています。
新婚当時から姑とウマが合わず、マザコンな夫に愛想尽きた事が離婚原因で我慢の限界に達し、今後は親権問題で争う形になると思..もっと見る
亡くなった父は再婚で先妻との間に子供がいる事が発覚しました
先日父が亡くなりました。(母は既に他界)
遺産を相続する為に、父の戸籍謄本等を取り寄せそこで初めて分かった事なのですが、父は再婚だったようで、先妻との..もっと見る
主人から離婚の申し入れがありました。
最近、主人から離婚の申し入れがあり今後どうすればいいのか一人で悩んでいます。
結婚当初から性格の不一致で小さな喧嘩は絶えませんでした。
私がもう少..もっと見る
父の兄妹は不仲です。
父の兄弟間で相続問題があります。
祖母が昨年末亡くなりました。(祖父は4年前に他界。)
父は次男で不仲の兄と妹の3人兄弟で今回の相続人はこの3人になり..もっと見る
借地の実家が空き家状態です
母が一人暮で暮らしていましたが、亡くなり空き家となりました。
実家は、借地で建物は父が建てたものを地主さんに地代を年払いしています。
地主さんには..もっと見る
離婚相手との相続について知識を得ておきたいので質問させて下さい。
前妻と8年前に離婚しました。
その相手との間に子供が1人(長男)います。
親権は向こうで、慰謝料を毎月支払い、長男は向こうが育てていっています。
3..もっと見る
いきなり離婚を言い出され、夫から家を出て行けと言われました。
頭金500万は夫の母の援助(将来同居の予定で部屋も用意)夫婦連帯債務で3000万円のローンを組み、持ち分2分の1ずつで、新居を購入して、住み始めて半年、いきなり..もっと見る
被後見人の離婚について教えてください。
今我が家は認知症の父の財産の取り合いで泥仕合をしている状態です。
恥部をお見せする様な形でどこで誰に相談すればいいのか分からずこの様なお話をするのは..もっと見る
父に内縁関係の女がいる事が発覚しました
父に内縁関係の女がいる事が発覚しました。
娘である私達には全く分からず住まいは私達が育った横浜の自宅とその女の家を行ったり来たりする二重生活だったよ..もっと見る
借地権について教えて下さい
私の親が所有している土地に借地人が住んでいます。
築65年のぼろ家で地代は年⚫️万円頂いています。(契約書等は交わしていません)
最近になってこの家を新..もっと見る
離婚時の財産分与について質問です。
妻と離婚をしようと考えています。
結婚当初から性格の不一致で苦しんできました。
ようやく吹っ切れてきたところ2年前に父親が他界。
それと同時に別..もっと見る
母親はグループホームで生活しています。
父親が5年前に他界し、母親は現在グループホームで生活しています。
横浜にある実家(父親名義のままです)は今誰も住んでおらず空き家です。
現在は小生が..もっと見る