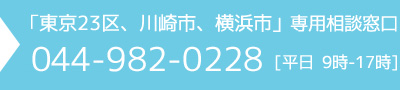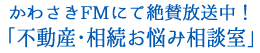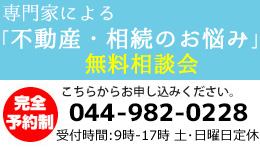遺言状の書き換え防止方法があれば教えて頂きたい
(東京都北区在住K様)
相続に関して教えて頂きたいことがあり、メールしました。
父は5年前から内縁の女性と暮らしています。
母は7年前に病死で他界しています。
そこでご相談です。
最近姉と相続のことで話し合いを持つことが多くなってきました。
それは内縁の女性の存在です。
父は元々地主の倅で今でも店舗や賃貸マンション等複数所有しており、不動産を中心に10億円ほどの資産があると思います。
私は内縁の女性の存在を3年位前に知ったのですが相続のこともあり、姉との話し合いにより、入籍はせずに内縁関係にて同居しようということにしておいてほしいと父には話しておりました。
しかしながら、今年に入ってその女性から「世間体が悪いので入籍したい」という申し出がありました。
父の人生ですからとやかくいう事は出来ないのは承知しております。
よって我々姉弟としては入籍に反対はしませんが、将来の事も考え遺言状を作ろうということになりました。
条件としては
現金を何千万円(まだ未確定)かを内縁の女性が相続するが、その他は遺留分も含めて相続を放棄すると言う内容にしてもらいたいと考えています。
なぜこの様な文面になってしまうかと思いますと、内縁の女性は派手で見栄っ張りな面があり、正直なところ私達は毛嫌いしています。
どうも父が騙されている様な気がしてならないのです。
よって子である我々は彼女をあまり信頼していません。
そのため、遺言状で作ったとしても、将来的に彼女の要望で父が書き換えてしまう危険性があります。
そこで、遺言状の書換えを防止する有効な手段はないでしょうか?
それが今の私達の一番の悩みなのです。
たとえば、公正証書遺言状の中に、「長男、長女の同意がない限り本遺言状の後に作成された遺言状は全て無効である」という事項を公証役場にて遺言しておくことは法律上できないのでしょうか?
遺言は期日が新しいものが有効であるというのは存じ上げております。
気の弱い父が彼女に依願され遺言状を書き換えられる可能性は十分あると考えられる為、私達としては父が生前の間に未然の措置を取っておきたいのです。
是非お知恵を貸して下さい。
私達にとって死活問題ですし、亡くなった母の事を考えると絶対に彼女に財産を渡したくないというのが本心です。
父は5年前から内縁の女性と暮らしています。
母は7年前に病死で他界しています。
そこでご相談です。
最近姉と相続のことで話し合いを持つことが多くなってきました。
それは内縁の女性の存在です。
父は元々地主の倅で今でも店舗や賃貸マンション等複数所有しており、不動産を中心に10億円ほどの資産があると思います。
私は内縁の女性の存在を3年位前に知ったのですが相続のこともあり、姉との話し合いにより、入籍はせずに内縁関係にて同居しようということにしておいてほしいと父には話しておりました。
しかしながら、今年に入ってその女性から「世間体が悪いので入籍したい」という申し出がありました。
父の人生ですからとやかくいう事は出来ないのは承知しております。
よって我々姉弟としては入籍に反対はしませんが、将来の事も考え遺言状を作ろうということになりました。
条件としては
現金を何千万円(まだ未確定)かを内縁の女性が相続するが、その他は遺留分も含めて相続を放棄すると言う内容にしてもらいたいと考えています。
なぜこの様な文面になってしまうかと思いますと、内縁の女性は派手で見栄っ張りな面があり、正直なところ私達は毛嫌いしています。
どうも父が騙されている様な気がしてならないのです。
よって子である我々は彼女をあまり信頼していません。
そのため、遺言状で作ったとしても、将来的に彼女の要望で父が書き換えてしまう危険性があります。
そこで、遺言状の書換えを防止する有効な手段はないでしょうか?
それが今の私達の一番の悩みなのです。
たとえば、公正証書遺言状の中に、「長男、長女の同意がない限り本遺言状の後に作成された遺言状は全て無効である」という事項を公証役場にて遺言しておくことは法律上できないのでしょうか?
遺言は期日が新しいものが有効であるというのは存じ上げております。
気の弱い父が彼女に依願され遺言状を書き換えられる可能性は十分あると考えられる為、私達としては父が生前の間に未然の措置を取っておきたいのです。
是非お知恵を貸して下さい。
私達にとって死活問題ですし、亡くなった母の事を考えると絶対に彼女に財産を渡したくないというのが本心です。

鹿山 博樹宅地建物取引士の回答
(株式会社GMコーポレーション代表取締役)

ご存知のとおり、複数の遺言があった場合、一番新しいものが有効であるのが原則です。
民法では、遺言の撤回はいつでもできることになっており、また、同法1026条では、「遺言者は、その遺言を撤回する権利を放棄することができない。」と規定されています。
ですので、「公正証書遺言状の中に、「長男、長女の同意がない限り本遺言状の後に作成された遺言状は全て無効である」という事項を公証役場にて遺言しておくこと」はできません。
それでも、とにかくお父様が遺言をしておくことが大事です。
それと可能であれば、お父様の後妻の方に遺留分放棄の許可審判申立手続きを家庭裁判所でしてもらった方がいいと思います。
あと、後妻の方には、お子さんはいらっしゃらないのでしょうか。
できれば、その推定相続関係を確認しておいた方がよいでしょう。
万一後妻の方に相続されてしまったときには、後妻の方の死後は誰に相続されるのか、もし後妻の方に実子、養子がいらっしゃらなければ、あなた方が養子になれば、最終的に相続でお父様の遺産を「取り戻す?」ことができるかもしれません。
「後妻の方の養子になる」というのは、扶養義務を生じるという問題等もありますし、このようなご相談の回答としては妥当なものではないかもしれませんが、まったく検討するに値しないとまでは言えないのではないでしょうか。
民法では、遺言の撤回はいつでもできることになっており、また、同法1026条では、「遺言者は、その遺言を撤回する権利を放棄することができない。」と規定されています。
ですので、「公正証書遺言状の中に、「長男、長女の同意がない限り本遺言状の後に作成された遺言状は全て無効である」という事項を公証役場にて遺言しておくこと」はできません。
それでも、とにかくお父様が遺言をしておくことが大事です。
それと可能であれば、お父様の後妻の方に遺留分放棄の許可審判申立手続きを家庭裁判所でしてもらった方がいいと思います。
あと、後妻の方には、お子さんはいらっしゃらないのでしょうか。
できれば、その推定相続関係を確認しておいた方がよいでしょう。
万一後妻の方に相続されてしまったときには、後妻の方の死後は誰に相続されるのか、もし後妻の方に実子、養子がいらっしゃらなければ、あなた方が養子になれば、最終的に相続でお父様の遺産を「取り戻す?」ことができるかもしれません。
「後妻の方の養子になる」というのは、扶養義務を生じるという問題等もありますし、このようなご相談の回答としては妥当なものではないかもしれませんが、まったく検討するに値しないとまでは言えないのではないでしょうか。