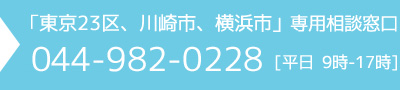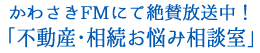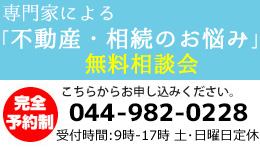相続対策を考え始めたところです
(東京都港区在住N様)
いろいろと今後の事を考え相続対策を考え始めたところです。
父は既に3年前に他界しており、母が他界した場合、相続人は兄と私の2人です。
最近母に確認したところ自宅以外の現金は父から相続したものを含め1億円位だそうです。
贈与税は年間110万円まで非課税であると聞き、兄、兄の妻、私、私の妻、に、110万×4人を毎年贈与する対策を考えています。
この対策は税務上問題ありますか?
あと今後私共に考えられる問題点について、アドバイスを頂きたくまた、その他問題がありましたらアドバイスをお願い致します。
例えば下記3点に関して質問したいです。
①生前贈与したお金は、相続時にどうなるのでしょうか? 相続時に清算したりするのでしょうか?
②相続の時に課税対象になる、5,000万円を母親の生前中に 相続人である我々に分けてしまう最善の方法はありませんか?
③私共の子(つまり母からすると孫)に贈与した場合も 同様に年間110万円までは非課税になるのでしょうか?
今のところ思いつく質問はこの3点ですが他にも何かアドバイスがあれば教えて頂きたいと思っています。
父は既に3年前に他界しており、母が他界した場合、相続人は兄と私の2人です。
最近母に確認したところ自宅以外の現金は父から相続したものを含め1億円位だそうです。
贈与税は年間110万円まで非課税であると聞き、兄、兄の妻、私、私の妻、に、110万×4人を毎年贈与する対策を考えています。
この対策は税務上問題ありますか?
あと今後私共に考えられる問題点について、アドバイスを頂きたくまた、その他問題がありましたらアドバイスをお願い致します。
例えば下記3点に関して質問したいです。
①生前贈与したお金は、相続時にどうなるのでしょうか? 相続時に清算したりするのでしょうか?
②相続の時に課税対象になる、5,000万円を母親の生前中に 相続人である我々に分けてしまう最善の方法はありませんか?
③私共の子(つまり母からすると孫)に贈与した場合も 同様に年間110万円までは非課税になるのでしょうか?
今のところ思いつく質問はこの3点ですが他にも何かアドバイスがあれば教えて頂きたいと思っています。

野口良子税理士の回答
(GALAP税理士法人)

贈与税の基礎控除額(年間110万円)を利用して、将来見込まれる相続財産の移転を進めることは相続税対策として有効です。
ただし、相続税対策として留意しておくべき点があります。
それは、「連年贈与」に該当してしまうリスクがあるというものです。
連年贈与とは、毎年繰り返し贈与することを言いますが、これが相続税上何が問題になるのかといいますと、例えば、毎年、子供に100万円ずつ20年間にわたって贈与する」と契約をしたならば、1年ごとに100万円の贈与を受けると考えるのではなく、契約をした年に、有期定期金に関する権利(20年間にわたり毎年100万円ずつの給付を受ける権利)の贈与を受けたものと捉えられ、当初の年に2000万円の贈与に対する贈与税が課せられてしまうということです。
これを回避するためには、その贈与が法的に有効な贈与なのかどうかを立証できるように準備しておくことです。
具体的には、
・受贈者(兄、兄の妻、本人、本人の妻)が贈与を受けた事を知っていること。
・贈与契約書を作成していること(できれば毎年)。
・受贈者が贈与財産を管理していること。
などが有効であると考えられます。
これ以外にも事実認定として有効な手段がありますので、財産の状況によりご相談に応じさせていただきます。
また、3点のご質問については、
①生前に贈与されたお金のうち、相続開始前3年以内に贈与された財産については、その贈与財産を相続税財産に加えて相続税を計算しなければなりません。
ただし、贈与税と相続税の二重の負担にならないように、「贈与税額控除」といって相続税額から事前に納税された贈与税を控除し税負担の調整が図られることになっています。
②お母様の5000万円を生前中に分けてしまう方法として考えられるものの一つとして「相続時精算課税制度」があります。
この制度は、贈与時に贈与財産に対する贈与税を申告・納付し、その贈与者の相続時に全ての贈与財産の価額を相続税の課税価格に加算して計算した相続税から、すでに納付した贈与税額を控除して納付すべき相続税額とする制度です。
①のケースでの利用も有効かと思われます。
この制度のメリットは、贈与時に2500万円までの特別控除額がありますので、この金額までは贈与税が発生せず、この金額を超えた場合でも一律20%の税率(通常の贈与税の税率は累進課税となっており、この税率よりも高くなるケースが多いようです。)で済むという点です。
デメリットは、一旦相続時精算課税制度を選択すると、その贈与者については従来からある110万円まで非課税である暦年課税制度には戻れないという点ですので、選択の際には留意が必要です。
③ご質問者のお子様も同じく年間110万円の基礎控除額があります。
前述のとおり、推定相続人(兄、本人)に対しては、相続開始前3年以内に贈与された財産は相続税財産に加算して相続税を計算する必要がありますが、孫については、遺言により財産を取得しない限り、この3年以内贈与加算の対象にならないので、節税メリットがあります。
ただし、贈与が法的に有効か否かの立証をする際に、受贈者が未成年の場合には、その立証が難しくなることが考えられます。
したがって、贈与契約書の作成や、金銭の引き渡しの証拠として手渡しではなく振込を利用するなど特に留意が必要となります。
また、子又は孫に対する贈与については、「教育資金の一括贈与に係る贈与税の非課税」という特例もありますので、お気軽にご相談下さい。
質問の訂正となりますが、②の相続税課税対象の5,000万円は本来、1億円又は基礎控除後の3,000万円が妥当かと考えられます。
ただし、相続税対策として留意しておくべき点があります。
それは、「連年贈与」に該当してしまうリスクがあるというものです。
連年贈与とは、毎年繰り返し贈与することを言いますが、これが相続税上何が問題になるのかといいますと、例えば、毎年、子供に100万円ずつ20年間にわたって贈与する」と契約をしたならば、1年ごとに100万円の贈与を受けると考えるのではなく、契約をした年に、有期定期金に関する権利(20年間にわたり毎年100万円ずつの給付を受ける権利)の贈与を受けたものと捉えられ、当初の年に2000万円の贈与に対する贈与税が課せられてしまうということです。
これを回避するためには、その贈与が法的に有効な贈与なのかどうかを立証できるように準備しておくことです。
具体的には、
・受贈者(兄、兄の妻、本人、本人の妻)が贈与を受けた事を知っていること。
・贈与契約書を作成していること(できれば毎年)。
・受贈者が贈与財産を管理していること。
などが有効であると考えられます。
これ以外にも事実認定として有効な手段がありますので、財産の状況によりご相談に応じさせていただきます。
また、3点のご質問については、
①生前に贈与されたお金のうち、相続開始前3年以内に贈与された財産については、その贈与財産を相続税財産に加えて相続税を計算しなければなりません。
ただし、贈与税と相続税の二重の負担にならないように、「贈与税額控除」といって相続税額から事前に納税された贈与税を控除し税負担の調整が図られることになっています。
②お母様の5000万円を生前中に分けてしまう方法として考えられるものの一つとして「相続時精算課税制度」があります。
この制度は、贈与時に贈与財産に対する贈与税を申告・納付し、その贈与者の相続時に全ての贈与財産の価額を相続税の課税価格に加算して計算した相続税から、すでに納付した贈与税額を控除して納付すべき相続税額とする制度です。
①のケースでの利用も有効かと思われます。
この制度のメリットは、贈与時に2500万円までの特別控除額がありますので、この金額までは贈与税が発生せず、この金額を超えた場合でも一律20%の税率(通常の贈与税の税率は累進課税となっており、この税率よりも高くなるケースが多いようです。)で済むという点です。
デメリットは、一旦相続時精算課税制度を選択すると、その贈与者については従来からある110万円まで非課税である暦年課税制度には戻れないという点ですので、選択の際には留意が必要です。
③ご質問者のお子様も同じく年間110万円の基礎控除額があります。
前述のとおり、推定相続人(兄、本人)に対しては、相続開始前3年以内に贈与された財産は相続税財産に加算して相続税を計算する必要がありますが、孫については、遺言により財産を取得しない限り、この3年以内贈与加算の対象にならないので、節税メリットがあります。
ただし、贈与が法的に有効か否かの立証をする際に、受贈者が未成年の場合には、その立証が難しくなることが考えられます。
したがって、贈与契約書の作成や、金銭の引き渡しの証拠として手渡しではなく振込を利用するなど特に留意が必要となります。
また、子又は孫に対する贈与については、「教育資金の一括贈与に係る贈与税の非課税」という特例もありますので、お気軽にご相談下さい。
質問の訂正となりますが、②の相続税課税対象の5,000万円は本来、1億円又は基礎控除後の3,000万円が妥当かと考えられます。